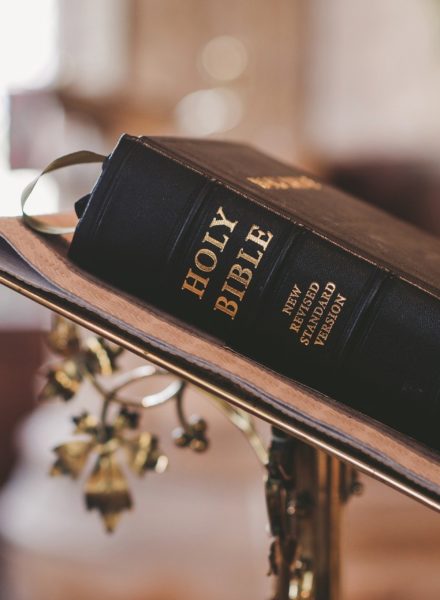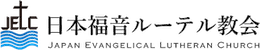るうてる2025年10月号
温故知新『神はわがやぐら』
九州学院チャプレン 日笠山吉之
「神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。」
(詩編46・2)
10月といえば私たちルーテル教会では宗教改革の月として広く認識されていますが、ルターの宗教改革については既にたくさんの牧師たちが語ってこられましたので、私は彼が書き残した賛美歌について書きたいと思います。
ルターは言わずと知れた偉大なる説教者にして牧会者で、かつ膨大な著作を書き残しましたが、音楽家の顔も持ち合わせていました。ルターはリュートという現在のギターによく似た楽器をつま弾きながら、テノールの美声で歌ったと言い伝えられています。そうして生み出されたのが、40曲以上にのぼる賛美歌です。中でも最も有名なルターの賛美歌と言えば、教会賛美歌450番の「力なる神はわが強きやぐら」(通称「神はわがやぐら」)でしょう。宗教改革を覚える10月に入ると、この賛美歌の出番はどこの教会でも格段に多くなるのではないでしょうか?私が勤める九州学院でも、この賛美歌は10月の歌として毎年選ばれています。終始四分音符で刻まれた確固とした音型で歌われる旋律は、明朗で力強く、歌っていると元気が出てくる賛美歌だと思います。この賛美歌の旋律を使って、バッハやメンデルスゾーンが作曲した『カンタータ第80番』や『交響曲第5番』も名曲として知られています。
ところが、私たちに最もなじみのあるルターのこの賛美歌の原曲は、リズムが多少異なっているのです。2021年に出版された『教会讃美歌増補 分冊Ⅰ』をお持ちの方は、16―1番を開いてみてください。その譜面を見ると、二分音符が主体となっているものの四分音符や八分音符まで使われていて、シンコペーションが随所に登場するやや複雑なリズムで書かれています。そもそも当時の記譜法にならって拍子の記載がありません。だから、これを大人数で声を合わせて歌うのはなかなか難しいのではないかと思います。したがって、この賛美歌はもともと信仰者が一人静かに自らを省みて、神に祈りをささげる際に歌われることを想定して作られたのではないか?と言われています。実際、ルターがこの賛美歌を書いた時期は、宗教改革ののろしを上げて意気軒高としていた時ではなく、その後の改革運動がなかなかうまくいかず壁にぶち当たって気持ちがふさいでいた頃でした。そのような時に、ルターを支えたのが「神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。」という詩編46編の御言葉だったのです。ルターは生涯にわたって精神的に何度も落ち込むことがありましたが、そのたびに彼を引き起こしてくれたのは聖書の言葉と、恵みの神への揺るぎない信頼―神はいつもわたしたちの避けどころであり、また堅固な砦でもあり、必ず私たちを守り、助けてくださる―だったのではないでしょうか。賛美歌の特徴の一つは、信仰を共にする兄弟姉妹たちと共に歌うという共同性ですが、時には一人静かにじっくりと歌詞を味わい、口ずさんでみるのも有益でしょう。
なお、このルターの代表的な賛美歌「力なる神はわが強きやぐら」(四分の四拍子で書かれたもの)は、ナチス・ドイツの時代に行進曲風に編曲され、盛んに演奏されました。それで、戦後ドイツやアメリカで出版された賛美歌集では、ルターの原曲版(拍子がないもの)も一緒に掲載されるようになり、今ではそちらの方が主に歌われているようです。このたび日本のルーテル教会も、『教会讃美歌増補分冊Ⅰ』の出版によってようやくその流れに追いつくことができました。聖書翻訳にしても、あるいは賛美歌や式文の改訂にしても、罪深い人間の歩みと歴史の中で、絶えず神のみ前で頭を垂れつつ、検証され、解釈され続けていく必要があるのではないかと思います。
ルターは言いました。「恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ」と。私たちもまた神の恵みに包まれながら、説教を通して、あるいは自らも聖書を開くことによって、信仰を見つめ直す日々でありたいと思います。
エッセイ「命のことば」 伊藤早奈
(67)「本当は」
「悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを愁いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば、主があなたがたを高めてくださいます。」(ヤコブの手紙4・9~10)
「おはよう」笑顔でそう言われたその人は、昨日自分のベッドのまわりのカーテンを閉め切って泣いておられました。お医者様の話をご家族と聞かれ、しばらく一緒におられたご家族の帰られた後、その人はカーテンの向こうで一人、泣いておられました。
そのような様子だった人が、次の日にっこりして「おはよう」とおっしゃられたのです。良かったと思う反面、心配になりました。それに、時々悲しいのに笑ったり、苦しいときに頑張ったりする人がいます。それは周りの人たちに心配かけないように気を使っているだけなのかと思っていた私に、それだけではないことを教えてくれることがありました。
ある日「ふふーん」とハミングが聞こえました。それは一人でつまらなそうにしておられた人から聞こえた歌でした。ハミングはご機嫌なときにしか歌われないと思っていたのに、もしかしたらご機嫌になりたい寂しいときにも歌うのかもしれないと気付かされた気がします。
実は、私が受けている言葉のリハビリでもハミングで歌う練習も教わりました。笑っておられるから喜んでおられるとか、ハミングをしておられるからご機嫌なんだろうと思っていたし、悲しいのに笑顔の方々はきっと周りを心配させないためだけだろうと思っていましたが、もう一つ自分を支えるためという大切な意味があることを教えて頂いたようです。
一つだけではないのかもしれません。表面的なことだけでは分からないことがたくさんあるかもしません。でも、表面的だけではないあなたを神様はご存じです。
「全国の教会・施設から」㉙
日本福音ルーテル藤が丘教会
江越倫子(日本福音ルーテル藤が丘教会代議員)
秋、イチョウ並木の葉が紅葉する坂を上がって行くと、そこには藤が丘教会があります。かれこれ50年近く前、東教区城南神奈川地区で「新しいビジョン」が決定され、教区をあげて開拓伝道に力を注ぐことになり、各教会からの牧師、信徒で構成された委員会を中心に活動が始まりました。何回もの話し合い、詳細な調査をして計画は進められていく一方、当時のバブル経済の始まり、土地高騰。それでも皆さまの思い、祈り、多くの方々からの献金を頂き神様に導かれ、田園都市線沿線の藤が丘に「藤が丘教会」が誕生しました。最初はプレハブの会堂での礼拝でしたが、1988年12月、神様の恵みと祈りの満ちた新会堂での礼拝が守られました。
そして今年は宣教42年を迎えます。宣教40年の時に今までの感謝として地域に開かれた教会として歩みを始めました。2023年、コロナウイルス感染症が5類になった5月より毎月1回、地域の方々、信徒の知り合いの方々をお招きして「虹のひろば」という会を立ち上げ、委員会の方々が盛りだくさんのプログラムを企画。多くの方々が毎月楽しみに藤が丘教会にお越しくださいます。CSにも参加する子どもたちも増えて、日曜日の朝、子どもたちの声、トーンチャイムの演奏を聴くと心がほっこりとします。
今年はルーテル教会での牧師不足、今後の教会の状況等々を鑑みて、「これからの教会を考える会」を開き、ご意見、提案をもとに少しずつ信徒が担える事を始めています。藤が丘教会で長年言われ続けている「できる事をできる範囲でできる人がする。」というモットーのもとで礼拝にあずかる事ができ、信徒全員で神様のみ言葉を聞き、賛美歌を歌い、心を合わせて祈り、福音の宣教をしていく教会になりました。今までの恵み、祈りに感謝申し上げます。
熊本ライトハウス・熊本ライトハウスのぞみホーム
森田智博(熊本ライトハウス、熊本ライトハウスのぞみホーム施設長)
「隣人を自分のように愛しなさい」(マタイによる福音書22・39)は、私たちの施設が守り続けてきた基本理念です。
「熊本ライトハウス」の始まりは、慈愛園の創設者であるモード・パウラス宣教師が、約72年前に慈愛園乳児ホームで一人の目の見えない赤ちゃんとの出会いによるものでした。
その赤ちゃんを通して、神様のご計画である視覚や、聴覚に障がいを持つ子どものためのホーム制施設「熊本ライトハウス」が誕生したのです。
その後、時代と共に福祉ニーズは変わり、家庭復帰や社会への自立が困難な成人の方々の生活の場が切望され、1993年には、同一敷地内に成人の障がい者入所施設である「熊本ライトハウスのぞみホーム」が造られました。創設以来、私たちは日々の生活において、障がいを持ったことにより行くべき道を失いかけた人たちの光の家として、明るい光をともし続けてきています。
現在、熊本ライトハウス(児童)には、19名(定員20名)、のぞみホーム(成人)には、39名(定員40名)の利用者がおり、地域の方々や多くの関係者の方々に支えられ生活を送っています。施設行事としての地域交流夏祭りや、ライオンズクラブとの
共催で行うバザー、クリスマス会は、利用者の方々の楽しみであり、多くの地域の方たちも参加し、地域交流の一助となっています。また、施設内にはいまなお悠然と根を下ろし、神様と共に創設以来私たちを見守り続けている「大樹イチョウの木」があり、施設のシンボルとして利用者や職員、また地域の方々に親しまれています。
これまで長年にわたって利用者や、地域の方々に必要とされる施設であったように、これからも私たち職員一同は、支援を必要とするすべての利用者の先導者となり、神様と共にその笑顔をともす光となり、ぬくもりをともす光となって、その光を決して絶やさぬよう進んで参ります。
70有余年にわたって守り続けてきた、モード・パウラス宣教師の創設の理念を決してぶれることなく継承してきたことを誇りとし、ここで生活するすべての方々にとって今何が必要かを常に模索しつつ、歴史の継承と未来への改革を恐れることなく次の世代へ引き継いでいきたいと思っています。
改・宣教室から
小泉基(日本福音ルーテル札幌教会牧師・宣教室長)
西千津さん(カトリック円山教会)
小泉 西さんとは、外国人住民基本法の制定を求める北海道キリスト教連絡協議会(北海道外キ連)でご一緒させていただていますが、カトリック教会の担当部署で働いておられるのですよね。どんな部署で、どのような働きをなさるのですか。
西 ボランティアからはじまり、パート職員を経て2019年にカトリック札幌司教区職員として採用されました。担当しているのは主に難民移住移動者委員会です。働きには二つの側面があり、一つは司牧で教会の中心の働き。現在増えている外国籍信徒の多くは子どもの頃から教会に通い、信仰を培ってきた青年たちです。日本での生活の中で信仰を失わず、成長できるようにするのが大きな役割です。もう一つは、日本の教会や社会の中で必要とされている支援をどう提供するかです。言葉で苦労される方が多く、一見理解をされていないように見えたとしても、母語ややさしい日本語で説明すれば多くのことがわかります。また、在留資格で苦労している方もたくさんおられます。
小泉 外国の方々の支援には、難しさと喜びとがあると思います。
西 難しいと思うのは、信頼を得ることができない時です。誰もが何かを相談したいと思ったら、この人に全部話してもよいのかと考えると思います。もっと賠償金がもらえるという言葉を信じて、私たちから離れていく人もいました。「そんな甘い話はないから」と言っても分かってもらえない時はいつも歯がゆい思いをします。喜びは、相談者の笑顔に出会った時です。支援の最初は、本当に暗い顔です。そんな顔が少しずつ優しい顔になり、笑顔が見えた時、ホッとします。
小泉 西さんとキリスト教との出会いを教えていただけますか。
西 バブルの頃、海外旅行にあこがれて英会話教室へ通ったら、なぜか私にはキリスト教の話しかしない先生がいて、私は特別なのかも?と大きな勘違いもしました。それが最初のキリスト教との出会いです。しばらくしたら、その先生は違う生徒と結婚して、一気に現実に引き戻されましたが、キリスト教への関心はそのまま残り、今に至っています。
小泉 最後に、西さんが大切にしておられる聖句を教えていただけますか?
西 「地の塩、世の光」(マタイによる福音書5・13~16)です。20代の頃、留学生への支援をボランティアでしていた時、ある留学生から私たち支援者の働きが「地の塩、世の光」のようであり、とても大切な働きだということを信じてがんばってほしいと言われました。その時はピンと来なかったのですが、子どもが生まれて成長していく過程で「地の塩、世の光」のように生きて欲しいと思いました。私がいずれ入る納骨堂の墓碑にもこの言葉を刻みました。
小泉 どうもありがとうございました。すべての外国人住民が暮らしやすい社会のためにともに働いていきましょう。
2026年教会手帳を発売開始いたします。
週間の聖書日課は、「改訂共通聖書日課」を
採用しており、「家庭礼拝のための聖書日課(ルーテル聖書日課を読む会発行)」と
対応しております。
お求め先は、全国のキリスト教書店まで。
また各教会でまとめてご注文の場合は、日本福音ルーテル教会事務局(電話:03‐3260‐8631/FAX:03‐ 3260‐8641)までお問い合わせください。
世界の教会の声
浅野直樹Sr.(日本福音ルーテル市ヶ谷教会牧師・世界宣教主事)
ルーマニアのルーテル教会
ルーマニア福音ルーテル教会は、大多数が東方正教会のルーマニアにあって規模は小さいですが元気な教会です。ペーター・キャライさんは、ルター派として多様性とエキュメニズムと奉仕を大切にしています。信徒リーダーとして奉仕やグローバルなつながりについてお話してくれました。
―教会での働きについて教えてください。
私が属する教会はルーマニア福音ルーテル教会です。ドイツ語の教会とハンガリー語の教会があって、私はハンガリー語の礼拝に通っています。
ルーマニアではほとんどの人がルーマニア正教会(オーソドックス)に属しているので、信仰面でも、国民性という点でも私は少数派です。そういうこともあり、私たちの教会は自分たちの個性を大切にしています。私は自分の教会で財務を担当していますが、昨年、教区常議員に選ばれたので教区の財務もしています。二重の意味でマイノリティーだからか、私たちはとてもオープンでエキュメニカルです。信仰的背景にも関わらず誰でも受け入れています。
―信徒リーダーとしてその恵みと課題を教えてください。
自分のスキルを用いて奉仕できることが恵みです。ただ私は博士課程で学びながら教会の仕事もしているので両立が大変で、教会の働きに十分時間をかけることが難しかったりします。
―ディアコニアに熱心な教会のようですね。
そうです。活発な年配者がたくさん居て、訪問したり、必要に応じて経済的なサポートもします。説教を届けたりもします。共に時間を過ごしお話を聞いたりするという支援です。また教会学校も頑張っています。毎週日曜日、子どもたちも教会で過ごしています。
―最近信徒リーダーセミナーに参加されましたが、何が収穫でしたか。
世界各地からリーダーが集まり、おのおのの教会が抱えるチャレンジを聞くことができ刺激になりました。また世界ルーテル連盟(LWF)の方策を学べたのはよかったです。エキュメニズムやディアコニアなど、私たちの取り組みと関連していたので励みになりました。
―共産主義時代は教会が疎外されました。その間、信仰はどのように成長しましたか。
クリスチャンの家庭に育ったせいか、共産主義の時代も信者であることに問題はありませんでした。私は運が良かったです。ただ大変だった人も居ました。特にルーテル教会の場合は深刻で、多くの司祭が投獄されました。
―LWFとのつながりは今のあなたにとってどんな意味がありますか。
小さな教会なので孤独を感じることがありますが、ルーテル教会は世界中どこにでもあって、支えてくれる誰かが居ると思えること、自分たちはもっと大きなつながりの一部なのだと思えること、孤独ではないというのが一番大きいと思います。
TNG委員会子ども部門主催「こどもキャンプ」報告
中島和喜(日本福音ルーテル大江教会牧師・こどもキャンプキャンプ長
8月5日~7日に小・中学生を対象としたこどもキャンプが東京教会を会場に開かれ、小学5年生~中学1年生まで計15名が参加しました。こどもキャンプは東京と広島を交互に開催地とし、広島では平和学習、東京では世界の国々の中から、一カ国を取り上げ学んでいきます。今年は東京開催だったので、2025年の世界祈祷日に指定されていた「クック諸島」について学ぶ時となりました。
テーマは「わたしはすばらしくつくられた」です。クック諸島は南太平洋に位置する15の島々からなる国で、人口は約2万人と少ないですが、豊富な自然の恵みを最大限に生かしながら生活しています。自然の恵みを大切にし生きていく人々は、創造の主を賛美すると共に、自らもまた神に創られた者としてすばらしくされている喜びを受け取っているのです。子どもたちには、そんなクック諸島の学びを通して「君たちもすばらしく創られた」ということを3日間通して伝えていきました。
クック諸島の歌や言葉を学んだり、伝統的な装飾品を作ってみたり。豊富に自生するココヤシがどれほどの用途に使われるかを知っていったり。そうした体験や学びを通して、私たちに与えられるものがいかに豊かであるか、そして私たちもいかに豊かなものとして創られているかを振り返り、神への感謝を覚える時となりました。
「わたしはあなたに感謝をささげる。わたしは恐ろしい力によって/驚くべきものに造り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか/わたしの魂はよく知っている。」(詩編139・14)
時に理想の自分から離れることはあっても、それでも自らをすばらしい者として喜び、主を賛美していく。そうして生まれていく感謝を抱えて生きていけるすばらしさを子どもたちはきっと受け取ったのだと、子どもたちの感想と、帰り際の笑顔から感じることができました。祈り、支えて下さった皆さまと、招き、導いてくださった主に感謝して、報告とさせていただきます。
九州教区ティーンズキャンプ2025【Pray for Peace】報告
安井宣生(日本福音ルーテル健軍教会・甲佐教会・阿久根教会・長崎教会牧師・九州教区教育部長
原爆投下から80年の時に若者たちと共に長崎の爆心地に立つこと、またこの時に紡がれる祈りの交わりに共に連なることを目的として、九州教区ティーンズキャンプを8月8日~10日まで開催しました。
原爆の被害もさることながら、加害も含めた戦争の痛みを知り、「黙とう」との掛け声でにぎわいがやみ、鐘の音(原爆により二つのうちの一つが失われたままでしたが、マンハッタン計画に関与した医師の孫であるカトリック信徒の呼びかけにより今年寄贈され、原爆前の二つに戻った)とせみ時雨に包まれる経験、命果てたと思われながらも再生した被爆クスノキの巨木に力づけられ、平和への祈りと共に再建されたカトリック浦上教会での祈りに連なり、信仰の友の被爆体験と平和への思いを受け取った自身も被爆者であるキリスト者の思いを受け止める。参加者それぞれが人生における大切な時間と出会いを経験する機会となりました。
参加者の感想をお分かちします。
山下倖來(日本福音ルーテル玉名教会信徒)
キャンプでは長崎で平和についての学習をしました。人権平和資料館や原爆資料館には被爆の恐ろしさを物語る写真や映像、体験談など様々な資料が置かれていました。それはとても気持ちが悪く、とても心が痛くなりました。まるで映画の世界のようで、ロシアやウクライナ、イスラエル、パレスチナなどで今も戦争が行われているにも関わらず、戦争はとても遠い存在だと思ってしまいました。
同時に日本は原爆が落とされた唯一の悲しい国、被害者の国、そうではなくて、日本も外国の人々に対して、ものすごくひどいことをしていたという事実を知りました。
8月9日11時2分、80年前に原爆が落とされた場所に行き、その場所で黙祷するというのは初めての経験で、テレビの前でする時とはまた違った気持ちになりました。
今の平和な暮らしがあるのは戦争の時代に生きたたくさんの人々の苦難や、平和な世界へ!という思い、そして神様からいただいた大きな愛、人を許し合える心があるからだということがわかりました。(原文ママ)
公益財団法人JELA主催「アメリカ・ワークキャンプ2025報告」
日本の若者16名が米ペンシルベニア州でボランティアワーク!
森一樹(公益財団法人JELA職員)
公益財団法人JELAが主催する「アメリカ・ワークキャンプ2025」が7月下旬にアメリカ・ペンシルベニア州で開催されました。このキャンプはアメリカの宣教団体Group Mission Tripsが、全米で展開している家屋修繕のボランティアキャンプにJELAチームとして参加し、現地の中高生とボランティアワークを行い、寝食を共にし、毎日聖書の御言葉に触れ神様のことを学ぶキャンプです。
今年は日本全国から16名の若者が参加しました。以下、感想レポートを一部紹介(原文ママ)します。全文はJELAのウェブページに掲載されていますので、二次元コードまたはインターネット検索からぜひご覧ください。
ワークチームに日本人がいないことを知った時、すごく不安で怖くなった。だが、メンバーはとても気さくでほとんど英語がわからない私に諦めずに伝えようとしてくれ、日本のことを知ろうとしてくれたり、学校の話をしてくれたりした。現地の方々の温かさと明るさに本当に救われたと思う。私にとってこれが1番神様の備えを感じた場面だった。(高校1年生)
ワークでは、ペンキ塗りや手すりの取り付けを行った。肉体労働をして役に立ったということはもちろんだが、家主と話していたときに「あなたたちが来てこうして話すことができて楽しい、日本からわざわざ来てくれてありがとう」と言われた瞬間、彼らの精神的な支えにもなれた気がして本当に嬉しかった。神様はきっと最高の出会いを「Equipped」してくださったのだと思った。(中学2年生)
このキャンプで「与えることは自分自身が満たされることにつながる」ことを実感した。作業中の疲れや不安も、誰かの笑顔や仲間の支えに出会うと消えていき、最後に残ったのは人のために行動する喜びだった。私はノンクリスチャンだが、皆と過ごす時間の中で、目に見えない大きな存在を少しだけ感じることが出来たように思う。(高校1年生)
日本福音ルーテル教会幼稚園保育園連合会夏の研修大会・総会」報告
竹田拓己(ルーテル幼稚園保育園連合会会長・大森ルーテル幼稚園園長補佐兼事務長)
日本福音ルーテル教会幼稚園保育園連合会夏の研修大会・総会が8月8日~9日の2日間、北海道札幌パークホテルで開催されました。北海道の地で研修を行う事は、初の試みでした。夏休みの時期が他地域と異なる北海道の先生方が参加することができるよう、例年8月下旬に実施していた研修を上旬に実施しました。
今までなかなか参加がかなわなかった北海道のめばえ幼稚園も今回参加してくださいました。めばえ幼稚園は築80年の園舎をもつ、歴史ある園です。今回の研修を機にめばえ幼稚園を訪問した先生方もおられます。良き交流が持たれたようです。それだけでも北海道で実施した意義はあったと思います。
1日目は、柴田愛子先生(りんごの木子どもクラブ代表)に「わたしの保育」と題してご講演いただきました。柴田先生の保育経験から、多くの話をしていただきました。柴田先生のお話は心に響くものがあります。聞いている先生方は、時に頷き、時に笑い、時に涙している姿もありました。心に温かさの残るすてきな話をしてくださり感謝しています。先生方に「あなたの思うままに子どもに寄り添って保育をしていいんだよ」とメッセージをいただいたように思います。心救われた先生方もいたのではないかと思います。
2日目は久保山茂樹先生(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム推進センター上席総括研究員兼センター長)に「インクルーシブな保育で共生社会の担い手を育む―子どもの視点で保育を見直しながら―」と題してご講演いただきました。
題名だけ読むと、難しいお話をされるのではと感じてしまいますが、久保山先生は「覚えなくてはいけない話、頭を使うような話はありません。むしろ心を使って聞いていただければ」と冒頭でお話しくださり、先生方の緊張をほぐしてくださいました。クラスの気になる子を思い浮かべてください。久保山先生は、先生方に「先生方はその子の全体を大きくったり捉える力があります。ゆったりと見てくれるから、その子は安心して先生のクラスに入ってくることができるんだと思います。もし、先生がその子の気になるところばかり見るようなまなざしを向けていたらどうでしょうね?保育者として障がいの専門家になる必要も療育のまね事をする必要もないと思います。保育者としてのまなざしを大切にしてほしいと思います。」と話されました。課題のある子に対してどうにかしなきゃいけないと思っていた先生方の気持ちを和らげてくださいました。
実りある研修になったことに感謝しています。総会も開かれ新たな役員も決定しました。神様の導きによって、その働きが守られることをお祈りください。
世界ルーテル連盟(LWF)定期理事会に出席して
本間いぶ紀(日本福音ルーテル甘木教会信徒・世界ルーテル連盟理事)
ルーテル世界連盟(LWF)の定期理事会が6月12日~16日にかけて、エチオピアの首都アディスアベバにて開催され、「Be my witness」(使徒言行録1・8)の主題聖句の下、理事会メンバーが集められました。わたしはLWF理事として2回目の定例理事会参加でした。エチオピアで開催するにあたり、エチオピア福音教会メカネ・イエスス(EECMY)が ホストチャーチとなり、レセプションへの招待や主日礼拝への参加を受け入れてくださいました。主日礼拝はEECMYのある教会に行ったのですが、決して小さくはない礼拝堂に人が隙間なく座り、屋外にも人があふれており、熱い活気を感じました。LWFとEECMYは性的少数者への理解という点において意見が対立していた過去があります。それでも同じ神様のもとに集まる兄弟姉妹として、賛美の時を共に持つことができ、ルーテル教会のコミュニオンを体験できました。
定期理事会では組織の方針、神学的・人道的な各プロジェクト報告、財務報告などを行います。特に今回は、2030年開催予定の第14回LWF総会をドイツ南部バイエルン州のアウクスブルクで開催することが決定しました。1530年のアウクスブルク信仰告白から5百年の年に、その地で総会が開催されるということは、ルーテル教会として大きな意味があると考えます。
これから第14回総会に向けてさまざまな準備が進んでいきますが、加盟教会が今からできることとして、ユースの参加を増やすということが挙げられると思います。前回の第13回総会は日本福音ルーテル教会から計5名が参加しましたが、ユースは私のみでした。地理的事情はありますが、ヨーロッパや北米、南米に比べて、やはりアフリカ地域やアジア地域からのユース参加者は少ないと感じたことを覚えています。LWFはあらゆる活動においてユースの参加を広く受け入れており、リーダーキャンプや聖研などのユースの活動も積極的に支援しています。
理事や、牧師としての働きを持つユースだけでなく、すべてのユースに開かれています。わたしはLWFの活動を始めるまで、LWFについて全く知らずにいました。同じように日本福音ルーテル教会のユースにはまだ知らない人がたくさんいると思います。私一人の力には限りがあるので、教会や教区など日本福音ルーテル教会という「組織」として、ユースを支えていただければと思います。そして、その支えこそが次世代に実を結ぶ枝になると考えます。2030年の第14回総会には日本からユースの参加者が増えることを期待します。
毎度のことですが、わたしは仕事の休みをもらい、飛行機を乗り継ぎ、会議に参加します。心が落ち着かないこともあります。しかし、どこに行っても会議中には礼拝があり、キリストの恵みを分かち合います。わたしたち一人一人がどこから来て、そしてどこに行こうともキリストが共にいるということを今回も強く感じることができました。
最後になりましたが、皆さまのご支援とお祈りに感謝いたします。そしてこれからもLWFの活動が神様によって守られ、証人としてキリストと共に歩めるようにお祈りください。