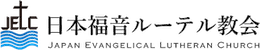るうてる《福音版》2007年3月号
バイブルエッセイ 「見上げてごらん、夜の星を」
東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった
マタイによる福音書2章9節(日本聖書協会・新共同訳)
先日、友人からメールが届きました。数少ないメル友の一人です。そこには、老いた母親の介護のことが綴られていました。「つらいんだろうなぁ」、「状況、厳しいんだろうなぁ」と思わず同情し、介護などしたこともないわたしまで、何だかつらい気持ちになって、沈み込んでいきました。でも、友人は、その最後に、「追伸」として「夕べは超寒かったです。自転車で帰る頃、夜8時半くらいかな。手袋がほしいくらい。星がすごく輝いて、きれいでした」と書き添えてありました。
夜道を自転車で帰りながら、友人は、きっと疲れていたと思うのですが、頭を上げて、夜空を仰ぎ、星を見たのですよね。そんな友人の姿を思い浮かべました。夜空にまたたく星の美しさに感動している友人の心がじわーっと伝わってきました。とたんに、こちらまで、「やったぜ、そうだ」とばかりに、うれしい気持ちになり、元気になりました。
40年以上前だったでしょうか、“スキヤキソング”と呼ばれ、日本のみならず世界のあちらこちらで口ずさまれた「上を向いて歩こう」という歌がありましたね。多くの人が共感したのでしょうね。上を向いて、天を仰ぎ見つつ生きようと。
讃美歌にもありますよ。“スルスムコルダ”とも呼ばれる歌で、「心を高くあげよう」という歌い出しです。歌っていると、背筋を伸ばし、頭をあげて歩もうという気にさせられます。「心を高く上げよう。神のみ声に従い、ただ主のみを見上げて、心を高くあげよう」。
聖書の神様も「さあ、目をあげて」と言っておられます。ある時、アブラムという人に対して、「天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみるがよい」と言われました。その時、アブラムはふてくされていました。「わが神、主よ。わたしに何をくださるというのですか。わたしには子供がありません」と、ぼやいているのす。そんな彼を、神様は夜の闇にひっぱりだし、星を見せました。そして、「あなたの子孫はこのようになる」と約束されたのです。
「人生、真っ暗闇」とつぶやき、そのたびに、うなだれるわたしたちです。生きていること自体、常に闇と隣りあわせというか、「同行二人」のような気がしています。そして、闇に飲み込まれ、引きずりこまれていく自分を感じます。その重圧に押しつぶされて、あえぎます。出口が見つからず、途方に暮れてしまいます。そんな時こそ、上を向いて、天を仰ぎ見ようではありませんか。
天、そこは主なる神様の住まいです。真暗闇で八方ふさがりであっても、天はわたしに開かれています。その天を仰ぎ見、星の光を見出すなら、救い主のもとへと導びかれていくことでしょう。
M.T
心の旅を見つめて
堀 肇(ほり はじめ)/鶴瀬恵みキリスト教会牧師・ルーテル学院大学非常勤講師・臨床パストラルカウンセラー(PCCAJ認定)
心豊かな旅を送るために(最終回)
死が日常の外へ
私たちは人生をよく「旅」にたとえますが、旅であるならば当然旅路の終わりがあるわけです。季節で言うなら、それは秋の終わりから冬に向かう頃と言ってよいでしょう。人はここまでくると次の段階、つまり死とその彼方について考えざるを得なくなります。しかし現代のように医学が進歩し不治の病と言われていた病気も治るようになってきますと死の意識は遠のき、いつまでも生きられるような錯覚に陥るのではないでしょうか。
加えて現実に死を迎える場合も、現代では、いわゆる「畳の上」ではなく殆どが病院や施設であることが死を日常から外へ追いやり現実感を乏しくさせています。このような死の「周辺化」の現象は今後益々進むだろうと思います。日本のように死を忌む文化の中では、その傾向が強くなっていくのではないでしょうか。その意味で健康・長寿・生きがいの過度の強調は老いや死を受容しにくくさせてしまう可能性があるのではないかと思います。
そこは「わが家」でない
確かに誰もが健康で長生きできればと願います。そして現代はそれが可能になりつつあるような時代です。ですが、どんなに医学が進歩し科学が発達しても人は必ず死を迎えます。聖書は人間には「一度死ぬこと」(ヘブ9:27)が定まっていると敢えて語り、現実に目を向けさせようとしています。私たちはこの事実を厳粛に受け止め死に備えることが必要なのです。老後の備えはあっても死と彼方への備えがなければ本当に安心のできる旅とは言えません。それはちょうど目的地を定めず道中だけを楽しんでいる旅のようなものです。
C・S・ルイス(オックスフォード大学教授)はこの辺りの消息をこんなふうに述べています。「父なる神はみもとに帰る途中に居心地の良い宿をいくつか設けて私たちをいこわせて下さいますが、私たちがそれをわが家(天国)と取り違えることは決して奨励なさらないでしょう」と。彼は地上の生活を否定的に考えているのではありません。そこに「幸せな愛の語らい、美しい風景、素晴らしい音楽、友との楽しい団欒」もあると、その価値についても語っています。しかし、そこを「わが家」と考えてはいけないというのです。
最後の日であるかのように
さて、ここまで考えてきますと、その「わが家」をどのように心に留めつつ旅することができるのかという問いが出てきます。私はキリスト教徒ですから当然その立場から語ることになりますが、イエスが「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる」(ヨハ11:25)、「父の家には住む所がたくさんある」(同14:2)と語られた言葉によって「復活」と「わが家」を信じて旅を続けているのです。
けれども、この旅の終わりがいつなのかわかりませんから、どれだけ長生きする時代になっても、遥か先のことと考えてはならないと思うのです。中世の修道士トマス・ア・ケンピスの祈りはまさにそのことを教えようとしているものです。「一日がなにをもたらすか、いったい、誰にわかりましょう? ですから神さま、一日をこの世における最後の日であるかのように生きることができますように……」。不思議なことですが一日を「最後の日」であるかのように考えると人生を前向きで丁寧に生きるようになってきます。何よりも人の心を優しくさせ、心の旅を豊かなものにしてくれるように思うのです。
※堀先生の「心の旅を見つけて」は、今回を持ちまして終了とさせていただきます。長い間ありがとうございました。
HeQiアート
Praying At Gethemane by He Qi, www.heqiarts.com
ゲツセマネで祈る
少し進んで行って地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。「アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしが願うことではなく、御心に適うことが行われますように」
マルコによる福音書 14章35~36節
たろこままの子育てブログ
番外編「いたわる時」
体の中でほかよりも弱く見える部分が、かえって必要なのです
コリント信徒への手紙一12章22節
私たちが通わせてもらっている整肢園も、この3月に今年は4名の卒園生を見送ります。 整肢園、つまり肢体不自由児通園施設にはどこかしら身体に事情を抱えた子が通ってきているのですが、中には体の自由だけでなく、意思表示も皆と同じようにするには難しいお友だちもいます(小太郎もそうです)。
お母さんが「うちが在園生の中でも一番重度よ」と笑うHちゃんも、晴れてこのたび卒園することになりました。6歳になる彼女は自分で立って歩く以前に、首も据わってません。寝返りも打てません。移動は特注の椅子で、黒子は専らお母さんの役目です。自力で痰を吐くことも出来ません(これも機械でお母さんが絶妙なタイミングで排痰します)。小太郎も自分でご飯は食べられないのですが、Hちゃんの場合は飲み込み自体が難しく、お腹に穴を開けてそこから大半の栄養を摂取していました。気温の変化にも弱く、発作もあり、訓練に通うのも大変な中、お母さんと二人三脚で歩む姿が今でも脳裏に浮かびます。
──こんな私たちは、場所が場所なら邪魔者扱いされて終わりでしょう。 小さいながらも園という集団生活、もしかしたら障害の程度によって差別もあるのではかと思われるかもしれません。が、不思議なことに園では、公園に行くにしても屋内の遊びでも、Hちゃんも一緒に楽しむにはどうしたらいいか、まずHちゃんにも無理なく参加してもらうにはどうしたらいいか、彼女を中心とする輪が広がっていた気がします。
普段「弱い」という単語は、どちらかというとマイナスイメージでとらえがちなもの、上の句のような切り口の文章は斬新ささえ覚えます。私たちもそんなHちゃんがいてくれたからこそ、一人一人であると同時に共に歩む仲間としてつながっていられたのだな、と実感させてもらえました。 喜ぶときは共に喜び、悲しいときには共に悲しみ、そして今日は皆でエールを送ります。卒園、おめでとう!