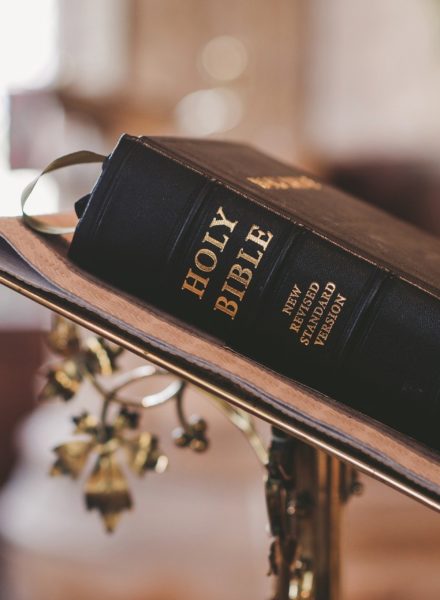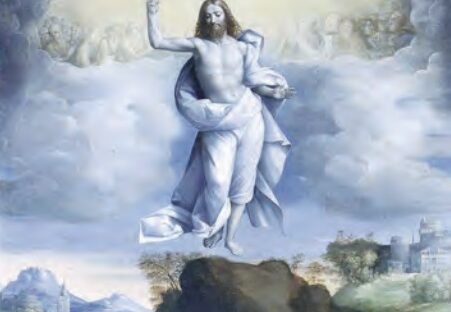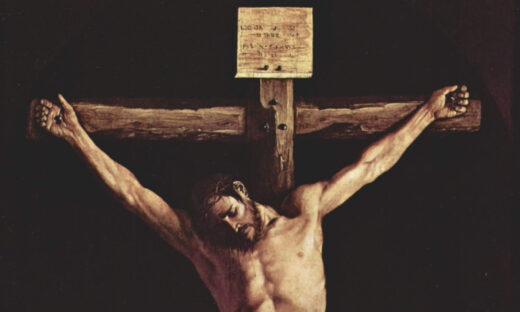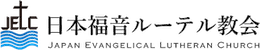「主に招かれた朝食」

小学校に勤務していたとき、毎朝、正門で子どもたちを迎えていました。学校が156段の階段の上にありましたので、子どもたちは息を切らして上ってきます。「おはよう」の一言から子どもたちの様子を観察します。階段を駆け上り笑顔いっぱいの「おはよう」、心配そうな不安な「おはよう」、「おはよう」の一言から子どもたちの心身の状態を感じ取ります。
教室に入っても覇気がなく、集中できない児童に「朝ご飯食べてきた?」と尋ねると、食べていなかったり、食べて来ても果物と飲み物、あるいはお菓子類だったり、孤食だったりすることが多くありました。朝食を欠食する者の割合は、男女とも、20歳代が最も多く、男性で37・0%、女性で23・5%、高校を卒業する18歳〜19歳で、急増し、20歳〜30歳代の一人世代では、朝食の欠食率が特に高いそうです。(厚生労働省「国民健康・栄養調査」2024年)
ヨハネ21章は、復活されたイエスが弟子たちに姿を現された三回目の記録です。21章は、1章から20章までのヨハネ福音書が完成された後で、補遺として付け加えられた部分だと考えられていますが、ガリラヤ湖でイエスに出会い、仕事も家族も残してイエスに従った弟子たちが再び復活されたイエスに同じ場所で出会うというのは重要な意味を持ちます。
弟子たちは、復活されたイエスに出会い、罪赦され、「父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす」(ヨハネ20・21)と約束されました。
しかしローマの兵卒に捕らわれるかもしれない、裏切り、見捨て逃げてしまった自分たちが、本当に赦されるのだろうか不安の中で過ごしていました。そしてイエスの弟子として仕えた日々を忘れたかのように、再びガリラヤ湖に戻り漁師を始めようとします。
「シモン・ペトロが「わたしは漁に行く」と言うと、」(ヨハネ21・3)他の弟子たちも「わたしたちも一緒に行こう」と言って舟に乗り込みます。決して前向きな転職ではなく、生きていくために漁師に戻るかという消極的な転職です。みんなで一緒にいれば何とかなるだろうという気持ちだったことでしょう。しかし転職はうまくいかず、夜通し舟を出して漁を続け、明け方になっても魚は一匹も捕れませんでした。そのとき「子たちよ、何か食べる物があるか」(ヨハネ21・5)と尋ねる者がいました。そのときまだ弟子たちはこの人がイエスであることに気づいていませんでした。漁師としてのキャリアも知識も豊富な自分たちが夜通し漁をしても一匹も捕れなかったのに、「舟の右側に網を打ちなさい。そうすればとれるはずだ」(ヨハネ21・6)と言われます。その通りに網を打ってみると、網を引きあげることができないほどの魚が捕れます。ここで弟子たちは初めてこの人が主であることに気づくのです。
主であることが分かると、ペトロは上着をまとい湖に飛びこみ、岸辺におられるイエスに走り寄ります。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて舟で陸に戻っていきます。陸にあがってみると、炭火がおこしてあり、魚がのせてあり、パンもあり、朝食の準備がされていました。そしてイエスはパンを取って弟子たちに与え、魚も同じようにして分け与えました。主の朝食に招かれた弟子たちは、どこまでもついていくと約束していながらイエスを裏切り、見捨てて逃げ去った自分たちの罪が赦されたこと、漁師として生きていこうとした弱さを自覚し、恵みにあふれた朝食を主イエスと共にし、再び立ち上がります。朝食を欠食する人が増えている時代ですが、朝食こそが1日の活力の源となり、学力、体力も朝食欠食が大きく影響することは明らかになっています。主に招かれた朝食は、再び立ち上がる人生の活力になることは言うまでもありません。聖餐を受けるたびに私たちは、主の食卓に招かれていることを再体験し、聖霊の導きによって力づけられます。全ての人が主の食卓に招かれていることに感謝し、共に主の食卓にあずかる喜びを多くの人と分かち合ってまいりましょう。
「奇跡の漁獲」コンラート・ヴィッツ作・1444年