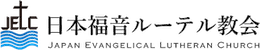不信仰を赦す神

「その子の父親はすぐに叫んだ。『信じます。信仰のないわたしをお助けください。』」(マルコによる福音書9・24)
「不信仰は主要な罪であり、すべての罪の中の罪であるのだから、罪の赦しとはもっぱら不信仰の赦しであるに違いない。」アメリカのルーテル教会の神学者であるロバート・ジェンソンは、その神学的自伝の中で自身の神学生時代を振り返り、当時強く影響を受けた19世紀スウェーデンの信徒説教者カール・オロフ・ロセニウスの言葉を紹介します。ロセニウスは、神が私たちの不信仰―神を信じられないということ―を赦されると言うのです。そしてジェンソンは、それまでこの当たり前のことに気が付かなかったと告白します。
1521年のヴォルムス国会で帝国アハト刑を受けたマルティン・ルターは、その帰途、誘拐を装って姿を消します。それは、彼の領主がルターを守るために行ったことでした。そこから1年近く、ルターは安全のためヴァルトブルク城にかくまわれて過ごしました。その間、精力的に取り組んだ執筆活動には、1522年に出版された新約聖書の翻訳も含まれます。ルター不在のヴィッテンベルクではしかし、ルターの同僚たちの手によって改革が急激に推し進められました。急進的な改革は街に混乱をもたらし、それは騒乱へと発展します。そのような中、1522年3月にヴィッテンベルクへ帰還したルターは、1週間にわたって説教を行います。それは、ヴァルトブルクに留まるように言う領主に対して、ヴィッテンベルクの教会の招聘を受けた牧師であることを根拠に自分の帰還を正当化した彼のアイデンティティによく合致したものでした。
同年5月から翌年初頭にかけて、ルターはペトロの手紙一の連続説教を行います。彼は、この書簡の冒頭に登場する「イエス・キリストの使徒ペトロ」の「使徒」という言葉を、「語る者」、「口頭で宣べ伝える者」と、若干強引とも思える解釈をして、「書かれた文字」ではなく、「生きた声」である説教を一ペトロ全体のテーマに据えます。そうして行われた連続説教は、ある種、福音説教についての説教と言えるような内容でした。福音説教とは何かを明確にし、説教者を育てることこそ、まだはじまったばかりの改革運動には何よりも必要なことだったのでしょう。ルターの同僚さえも改革を急進的に推し進め、混乱を引き起こす中では、福音をはっきりと語る説教こそが求められていたのです。混乱した街を回復させ、教会改革を進めるためにルターが最重要視し、また最優先に取り組んだことが福音の説教であるということは、言い換えれば、ルターがどれほど、説教―宣べ伝えられた神のことば―がその聞き手に働く力を信頼していたかということでもあります。説教を神が語る出来事として捉えていたルターは、他の何ものでもなく、説教をこそ、伝道の要に据えたわけです。
しかしルターは、人間の限界をも理解していました。たとえ説教者が神のみことばと格闘し、言葉を慎重に選んで十分に準備した説教をもって福音を明確に語ったとしても、それでも人間の力によっては、説教者自身にも、また、説教を聞く者にも信仰をもたらすことができないと、ルターは知っていたからです。語られたみことばを通してその聞き手のうちに信仰をつくりだすことができるのは神だけであると、信仰とは、神が私たちに働かれる神の業であると、ルターは知っていたからです。しかしだからこそ、ルターはみことばが語られることを、説教を、伝道の中心と理解しました。全力を尽くしてもなお不完全である人間を神があえて用い、信じられないという葛藤を生きる私たちに語るということである説教を通して働く神の恵みと憐みを、彼は信頼したのです。
宗教改革をおぼえるこの時期、私たちはあらためて立ち返ります。信じられない私たちに語りかけ、私たちの不信仰をも赦して私たちをその愛する子どもとする神こそが、私たちの神であるというよい知らせに、そしてそれが何よりも、説教を通して私たちのもとに届くのだということに。アーメン。
聖マリエン聖堂(ヴィッテンベルク)の祭壇画(下部) ルーカス・クラナッハ作・1547年







ケンブリッジ・フィッツウィリアム美術館所蔵-520x312.jpg)


ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵-520x312.jpg)