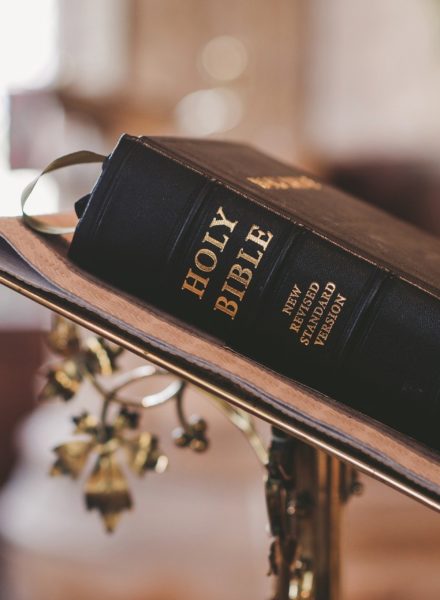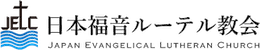るうてる2025年9月号
「創り主ファースト」
アメリカ福音ルーテル教会宣教師・神水教会・松橋教会・熊本教会国際礼拝牧師・九州ルーテル学院インターナショナルスクール小学部 安達均
「もし、だれかがわたしのもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、更に自分の命であろうとも、これを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない。」
(ルカによる福音書14・26)
1980年代は、私は日本光電という会社で、医用電子機器を開発する仕事に従事していました。
いっしょに開発を担当したメンバーに、「MEN FIRST」(メンファースト)という言葉を大切に取り組んでいたデザイナーのことを、近年よく思い出しています。
この言葉、一見、差別用語に聞こえ、「いったいどういうこと」と思う面があります。しかし、彼は決して「男性優先」という意味ではなく、「MEN」は男女に関係なく、「人間、人類」という意味だと言っていました。自分たちがデザイン・設計・生産する製品が、第一に人類にとって使いやすい、役立つものにするという意味を込めて、仕事に取り組んでいたのです。
主イエスは、ついて来る弟子や大群衆に向かって「父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない。」と言われるのです。このみ言葉、「いったいどういうこと」と思い、違和感さえ覚える方がいらっしゃると思います。しかし、主イエスが、真にわたしたち人類を愛し、教えてくださっていることが何であるか祈る中で、御言葉をじっくり聴くことの大切さがあります。そして、救い主イエスの言葉が、すばらしい、普遍的な正義に立った、本物の喜びに招いてくださっていると思うのです。
与えられた聖句は、私たちを愛するがゆえに、主イエスが十字架へ向かう旅の途中で、弟子たち、そして群集へと話された教えやたとえ話の一部です。イエスのこれらの話には、一貫したテーマがあるようです。御国はどんなところかを、たとえをつかって説明し、その御国の喜びに向かって歩むように招いてくださっているようです。
自分の家族や、自分の命を「憎まないなら」という言葉、「憎む」とはそもそもどういうことなのでしょう。自分の家族を愛すること、自分の命も大事にすることは、とても大切なことです。しかし、一番大切なお方が、天と地を創られ、やはり創造された植物、鳥、魚、動物、さらに人間が生きることができる環境、空気をも創り続けてくださっているのです。その全知全能なる創り主を忘れてしまい、家族や自分をファーストにしていないか。
もしそうであったとしたら、家族や自分の命も憎まなければならないと話された言葉もわかってくるように思うのです。
聖書において、御国の様子は、主イエスと人類の婚宴にたとえられていますが、人類を一人残らず、とことん愛してくださっている主イエスとの結婚に向けて、何がファーストなのか大切な心構えがあると思うのです。人間同士の結婚で心の準備、覚悟が必要なように、人類が真の備えをして、イエスとの婚宴、御国へ歩んでいくことが大切になります。
婚宴に招かれているのは、神が愛している人類全員です。ひとりひとりは、この世では、身分は違うし、文化も異なります。身近な家族や、この世の同胞と言われる人々ばかりではなく、自分にとっては敵だと思っていた人だって、含まれます。自分の気の合う人ファーストとか、この世で自分が住んでいる国ファースト、ではないわけです。
今でもたまに見かける1万円札の肖像となっていた福沢諭吉は、自分の子どもたちに「ひびのおしえ」というものを書いていました。その中に「てんとうさまをおそれ、これをうやまい、そのこゝろにしたがふべし。たゞし、こゝにいふてんとうさまとは、にちりんのことにはあらず、西洋のことばにてごつど(GOD)ゝいひ、にほんのことばにほんやくすれば、ざうぶつしゃといふものなり。」(※注(GOD)筆者加筆)という言葉が残っているそうです。日本の近代化に向けた教育機関、慶応義塾のために雇われた英語教師から聖書に触れる機会を得て、福沢諭吉も聖書の言葉に大きな影響を受けていたと想像します。
御国でも、この世においても、創り主ファーストという思いを忘れずに、自分も、家族も、この世のすべての隣人も大切にして、喜び、祈り、感謝して、この時代を歩めますように。
アーメン
エッセイ「命のことば」 伊藤早奈
(66)「まちのぞむ」
「なぜうなだれるのか、わたしの魂よ/なぜ呻くのか。神を待ち望め、わたしはなお、告白しよう/「御顔こそ、わたしの救い」と。」(詩編42・6)
まだ連絡が来ない、予定がどんどん立てられなくなるなぁ。ホントに待つって大変。不思議なことに今月になって焦りだした。連絡があると思うから、ないとイライラしてしまう。先月はなんとも思っていなかったのに、と考えたときに急に思い出したことがあった。
それは、何年か前に読んだ不思議な少女の話だった。その物語では人々は知らない間に時間どろぼうに自分たちの持っている時間を支配されてしまい気づかない。しかし、それは大変なこと。人々が時間に支配される前、今まで通り人々に時間を返すために少女がいつも通りに過ごす大切さを呟いていく。
少女は、特別何をするわけでもない。ただただ何もしないことの大切さを伝える。今、私は時間どろぼうに時間を取られてしまってはいないだろうか。時間どろぼうは、実際には居ないかもしれないけど、時間に支配されていることは少なくないような気がする。
でも、時間ってどこから来るのでしょうか。時計から?もしかして、いろんな仕事や、さまざまな予定を詰め込んでしまい、予定通り行かないとイライラしてしまったり怒ったり…。
それでも「今」というかけがえのない時は与えられています。あなたがどんなにイライラして過ごしていたとしても、ボーっと時間が過ぎたとしても、大切な誰かと過ごして短く感じたとしても、それは一人一人に与えられるかけがえのない時間。
時間にあなたが支配されているのでも、支配するものでもなく、あなたに与えられています。
「全国の教会・施設から」㉘
日本福音ルーテル横浜教会
亀本明美(日本福音ルーテル横浜教会代議員)
横浜は日本のプロテスタント教会発祥の地であり、ルーテル教会も1947年より牛島義明牧師がスタイワルト宣教師と共に東京地方での開拓伝道を開始しました。その年、牛島牧師が国立療養所を慰問した際、戦時中に中国で知り合った坂間保治氏と再会し、坂間氏宅(保土ケ谷区)にて家庭集会を開始。1948年3月には「日本福音ルーテル横浜教会」の表札を掲げ、毎週礼拝が行われるようになりました。同年11月の全国総会で教会設置が承認され、1949年に正式に成立します。
その後、礼拝場所は保土ケ谷から浅間町、三ッ沢を経て、1956年に松ケ丘に定着。地域に親しまれ、礼拝出席者は一時50名を超え、4人の牧師を輩出するほどに成長しました。1963年以降は横浜・横須賀・日吉の3教会合同による礼拝や親睦会、修養会などが開催され、豊かな交流を重ねましたが、次第に教会間のつながりが薄れ、そのころを語れる方が少なくなった現在では、礼拝出席は十数人へと減少しています。
2024年4月より河田優牧師が横浜・日吉両教会を兼任し、「キリストの体」としての一致を改めて実感する新たな歩みが始まりました。これまでに4度の合同礼拝と役員会が開催され、礼拝後には両教会の歴史を学び、証言を分かち合う時が持たれています。
小高い丘に建つ横浜教会堂は、神奈川県から土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)に指定され、7年に及ぶ協議と祈りの末、鉄筋で打ち込んだコンクリート枠にモルタルを吹き付ける「吹付法枠工」によって防災工事が完了しました。全境内地の売却も検討された困難な時期を経て、地域社会に対する教会の責任を果たす一歩が形となったのです。2025年5月18日、礼拝後に教会員がのり面工事の完成を一望できる場所に集い、イザヤ書26章「我らには、堅固な都がある」との御言葉を分かち合い、主こそ「とこしえの岩」であることを深く心に留めました。
今後もさまざまな課題に取り組みつつ、共に祈り、知恵を出し合い、主の御心を求めながら、私たちは宣教に励んでまいります。
キリスト教児童福祉会児童心理治療施設 こどもL.E.C.センター
松本祐一郎(こどもL.E.C.センター施設長)
近年、少子化が進行する一方で、児童虐待の件数は減少することなく増加傾向にあります。令和5年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は約22万5千件に達し、統計開始(平成2年)の約2百倍という深刻な状況となっています。
児童虐待を経験したこどもたちは、不安や恐怖に満ちた環境で生活し、身体的・心理的な傷を負っています。その結果、自己肯定感や基本的信頼の形成が困難となり、対人関係や感情調整に課題を抱えたまま日常生活を送るケースが少なくありません。この問題は長期にわたる「生きづらさ」へと直結し、成長や社会参加に大きな影響を及ぼします。
児童心理治療施設こどもL.E.C.センターは、熊本県で唯一の児童心理治療施設です。児童心理治療施設は、乳児院・児童養護施設等と同様に児童福祉法で定められた児童福祉施設であり、生活支援を基盤としながら、心理支援や家族支援、施設内に設置してある分教室と連携した教育支援に加え、外部医療機関や関係行政機関との協働を図り、包括的な心のケアを行っています。近年は、ゲーム依存やインターネット依存など、新たな課題を抱えるこどもへの対応も重要性を増しています。
私たちは、こどもたちが日々の生活や職員との関わりの中で、こどもたちが「大人に受け止められている」という安心感を回復し、困難に直面した際に適切に「助けて」と言える力を育むことを目指しています。
『わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している』(イザヤ書43・4『新改訳聖書』)
この聖句のように、これまでの人生の中で受けたさまざまな逆境体験によって、神の愛や他者への信頼を見失ったこどもたちが、再び「愛されている実感」を取り戻し、より豊かな人生を歩めるよう、私たちは支援を続けてまいります。
私たちの実践の様子やこどもたちの日々はホームページやInstagramで発信中です。ぜひ、アクセスしてください。
改・宣教室から
小泉基(日本福音ルーテル札幌教会牧師・宣教室長)
中本秀行さん(日本福音ルーテル挙母教会代議員・社会福祉法人オンリーワン理事長)
小泉 愛知県豊田市の障がい者施設オンリーワンは、地域の小さな作業所から始まった福祉施設のグループですね。今は、どのような事業を展開しておられるのですか?
中本 1998年に任意団体スモールワンとして発足し、2005年にNPO法人化しました。2011年に新たに社会福祉法人オンリーワンを設立し、事業を引き継ぎました。現在は障がい福祉サービス事業の活介護事業として定員20名を3事業、居宅介護事業、定員7名のグループホーム、定員10名の児童放課後等デイサービス、相談支援事業などを行っています。生活介護事業ではお菓子工房、飲食店、ものづくり(機織り)などを通して、障がいをもつひとたちの働く場・社会参加の場を運営しています。NPO法人の方もポースケと名称変更し、地域の方たちや生きづらさを感じている方たちの、居場所づくりをしています。
小泉 事業を通して大切にしておられることは、どのようなことですか。
中本 支える側、支えられる側という固定的な関係ではなく、「共に生きる」仲間としての関係性です。
小泉 中本さんが作業所を始めることになったいきさつを教えていただけますか?
中本 私には38歳になる知的に重度の娘がいます。障がい福祉サービスなどほとんど無いなか、子どもたちの今後を見据えて数人の母親たちが、親なき後のことも考えて居場所づくりをはじめたことが任意団体設立へとつながりました。
小泉 偏見もある中、大変なことも経験してこられたことと思います。
中本 始めたころは、福祉制度のない時代でしたので、資金や人材の確保に苦労しました。一般のボランティアの方たちも長くは続かず、途方に暮れることもありました。そんな中でも地道に支えてくださったのは挙母教会の教会員の方たちで、本当に感謝しています。以前に比べれば偏見は少なくなっていますが、真の理解という面はまだまだ難しいところもあります。私自身が、本当の隣人になることができたら良いなと思いながら関わりを続けています。
小泉 ありがとうございました。最後にキリスト教の出会いと愛唱聖句を教えてください。
中本 私はクリスチャンホームで生まれました。特に祖母が熱心な信仰者で、自然な形で教会に通うようになっていました。
愛唱聖句は「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ書43・4『新改訳聖書』)です。
世界の教会の声
浅野直樹Sr.(日本福音ルーテル市ヶ谷教会牧師・世界宣教主事)
サバ神学校でのリーダーシップ研修
7月7日〜12日、アジアの15教会から22名がマレーシアのサバ神学校に集まり、「神学によってどんな世界を形成できるか」などのテーマで、ジェンダー正義や変革をもたらすリーダーシップについて意見が交わされました。
参加者は事前に9カ月間のオンライン学習で交流を深め話題を共有し、テーマへの関わりを深めた後、サバに来て実際に顔を合わせ、神学、ジェンダー正義、リーダーシップの交差点を、おのおのの教会やコミュニティーの状況に照らし合わせて探りました。聖書研究やワークショップ、グループ討議を通じて、洗礼や全信徒祭司、按手といった神学のテーマを正当・平等の観点からディスカッションしました。
神学が個人の信仰形成だけでなく、共同体やシステムづくり、社会形成にも寄与することを目指す責任神学に議論は集中しました。LWF担当者キルネン牧師は責任神学について「神学が世界の形成にどう取り組めるかを問うこと」、「神学的作業が正義や尊厳、平等を実現するための取り組み」と述べています。
聖書の特定箇所が、家父長制や望ましくない文化規範を正当化するのに利用されてきた過去に触れ、どうしてそうなったのかについて活発な議論がありました。参加者たちは状況を踏まえながら聖書本文と向き合うことで新たな視点を得ることができ、そうした聖書の読み方が不正に立ち向かうためのツールになることを学びました。
女性教職者は按手を受けていても制約を受けることがあるなど、指導的立場にある女性神学者が置かれた立場の難しさが繰り返し話題になりました。女性も男性も、ジェンダー正義と平等性を踏まえてリーダーシップを追求する。今回のプログラムの趣旨がそこにあることをディスカッションから確認できました。
ワークショップでは神学的振り返りと相まって、個人および地域リニューアルの糸口となり得る変革的(トランスフォーマティブ)な学習を
体験しました。このセッションでは参加者がリーダーとして行動するうえで役に立つアイデアを思いつく材料を提供し、ジェ
ンダー正義、解釈学、セルフケア、プロジェクト企画、価値観ベースのリーダーシップ、LWF方策について学習しました。
キルネン牧師はこう締めくくっています。「忌憚のない会話ができ、お互いの励ましの場となりました。神の正義と恵みを映しだせる教会を目指そうという決意をもって、みなさんサバを後にしました。」
第30回東教区宣教フォーラム報告
平和の担い手として―祈りと行動を
八木久美(日本福音ルーテルむさしの教会代議員・宣教フォーラム実行委員会委員長
1945年8月の戦争終結から、今夏で80年を迎えます。世界では今も争いが絶えず、平和が脅かされています。武力で平和はつくれない│その言葉に耳を傾けながら、私たちは「平和の担い手」として何を思い、どう歩み始めるのか。その問いを胸に、第30回東教区宣教フォーラムが開かれました。
7月5日(土)午後、東京教会を会場に、「どうして戦争しちゃいけないの?―イスラエル軍元兵士が語る非戦論―」をテーマとしたフォーラムに110名超の来場者と、ライブ配信を通じ多くの方が参加しました(現在視聴可能です)。
礼拝説教「本当に重要なこと」、聖歌隊「諸国民、諸国、世界の主よ」に続き、第1部では、イスラエル出身で秩父在住の家具職人であり、元イスラエル軍兵士ダニー・ネフセタイ氏が自らの体験に基づき、戦争と人権について語りました。彼はパレスチナ人を‶敵„と教えられて育ち、軍に入隊しましたが、占領地で出会ったパレスチナ人たちが「自分たちと変わらぬ生活者」であると気づき、衝撃を受けたと語ります。
「‶敵„は教育によって作られる」「想像力が平和をつくる」と語り、暴力の連鎖を断つには、誰もが‶考え、疑い、行動する„市民になる必要があると訴えました。家具職人として「ちゃぶ台」を作る仕事になぞらえ、「武器でなく、顔を向け合って語り合える‶ちゃぶ台„をつくりたい」と語る姿も印象的でした。誠実に体験を見つめ、全身で語る姿から、非暴力と対話による生き方の力強さが会場に伝わってきました。
第2部では、ゼルダ・エドマンズ氏(ドキュメンタリー映画監督/通訳:中山康子氏)、市原悠史牧師、内藤新吾牧師が加わりパネルディスカッションが行われ、戦争と平和、加害と被害について語られました。
パレスチナでは、子どもたちも爆撃の恐怖の中で‶標的„となり、封鎖により支援が妨げられ、飢餓の犠牲も増えています。一方、日本では難民支援や人道的活動への理解が不十分な現実も浮き彫りになりました。「知る・想像する・語る」ことを恐れずに向き合う営みが、私たちが平和の担い手として歩む起点であるとディスカッションは静かに力強く語っていました。
「戦争を知らない時代」を生きる私たちが、どこに心をおき、他者の苦しみに目を凝らし、声を聞き、共に平和をつくるのか。週末の半日がその一歩を踏み出す機会となりました。秩父神社には、「よく見て・よく聞いて・よく話そう」の三猿の彫刻があるそうです。祈りと共に、私たち一人一人と教会も希望の通路となれるはずです。これからも「見る・聞く・考える・話す」を重ねながら、それぞれの場で歩みを続けていけたらと願います。
主の平和・感謝と共に
2025年九州教区平和セミナー報告
中島和喜(日本福音ルーテル大江教会牧師)
7月20日〜21日の日程で九州教区平和セミナーが熊本教会にて開かれました。
今年のテーマは「いのちを育む」です。「平和」という言葉から私たちがまず思うことは「戦争がない状態」です。しかし、私たちは戦争や暴力を知っていく時、その心には大きな悲しみや怒りが沸き起こります。それらの感情は、平和への働きを後押ししてくれるものでありますが、一方で自らを正義とし、あたかも神に成り代わるごとくに人を裁いていく危険を抱えるものでもあります。私たちがすべきことは人を愛することです。そのことを確かめるために今回の平和セミナーでは私たちの心が平和で満たされ、平和に向けて出発しようと語り掛けるものでした。
そのために、サブタイトルを「こどものせかい」としました。こどもは平和を最も体現する者。こどもの世界は真に平和に満ちています。私たちはそこから学ばなければなりません。決して、こどもだからできることなどと思わずに、この人たちこそが平和を知っているのだと。
そのことを学ぶために、今回は講師としてこうのとりのゆりかご当事者である宮津航一さんに講義をしていただきました。こうのとりのゆりかごとは、慈恵病院が運営する、何らかの事情で自分で育てることのできない赤ちゃんを匿名で預かる施設です。宮津さんはそこに預けられた1人目のこどもでした。宮津さんの講演は、3歳で預けられるという悲愴感にあふれてもおかしくない話を、それでもこうのとりのゆりかごが自分を救ってくれたという、愛の話として語って下さりました。私たちが悲しみからではなく愛から出発していくのだと。そのことの喜びを、宮津さんは身をもって教えてくれたように思います。
2日目にはそのことを参加者で話し合う時間が与えられました。皆さんの感想には、居場所、平安、平和、そういった言葉が語られ、私たちが愛を成していくのだという思いを、きっとそれぞれが受け取ったのだろうと思います。改めて、真に平和に満ちたセミナーであったとともに、ここから受けた平和を抱えて、今度は私たちが平和の使者として愛を果たしていきたいと感じる時でした。
サバ神学校でのリーダー研修報告
安田真由子(日本福音ルーテル都南教会信徒・アメリカ福音ルーテル教会(ELCA)ジェンダー正義コーディネーター)
「これからは『責任ある神学』を求めなければならない。これまでの『無責任な神学』への反省と共に。」世界ルーテル連盟(LWF)主催のリーダー研修で発せられた言葉です。研修はTheology, Gender Justice, Leadership Education(「神学・ジェンダー正義・リーダーシップ教育」)と題され、アジア各国の牧師、信徒を対象に、昨年12月〜今年6月にオンライン研修、7月7日〜12日に対面研修がマレーシアのサバ神学校で行われました。
対面研修の参加者は21名、スタッフ含め30名弱。わたしは企画者の一人として昨年5月から携わってきましたが、オンラインでの交流のみで直接会うのは初めての人たちと6日間一緒に過ごすのは、良くも悪くも緊張を伴います。現地に入るまで、どんな一週間になるのか、どんな人たちとどんな言葉を交わすのか、落ち着かない日々でした。
サバでは毎朝8時に聖書研究から始まり、講義やディスカッションを18時半まで行い、神学、ジェンダー正義、リーダーシップについて学びを深めていく濃密な時間を過ごしましたが、中でも特に印象に残った言葉や場面があります。
一つは、冒頭に引いた言葉。これは、伝統的な神学の「無責任」な側面が、人々の尊厳や命を奪ってきた歴史を示しています。「人はみな神様に愛され、平等だ」と語りながらも、人を分け隔て差別的に扱うような「神学」です。例えば、「女だから」という理由で牧師になることを許さないこと、「LGBTQ+の人たちは罪人だ、悔い改めるべきだ」と裁く「神学」。(主に男性の)牧師や教会役員がハラスメントや性暴力を振るっても、加害者の責任は不問にし、被害者に「赦しなさい」と諭す「神学」。中絶を認めないなど、性と生殖に関する健康と権利(SRHR)をないがしろにする「神学」。枚挙にいとまがありません。だからこそキリスト者一人一人が、より責任ある神学を模索、構築し続けていく必要があるわけです。
とはいえ、あらゆる人の人権と尊厳が尊重される神学を追い求め、実践していくことは簡単ではありません。年長のスタッフが、「生き延びるため、妥協しなきゃいけないことも多々あった」と語った時、目の奥が熱くなりました。人権や尊厳を諦めてしか生きられない命。そんな生を強制してきた教会に、社会に、憤りを覚えるのは当然ではないでしょうか。
そんな教会を変えていくのが研修参加者たちです。熱心に話を聞き、鋭い視点を持ち、活発に意見を交わす姿には励まされました。彼らは研修で得たことを活かし、それぞれの教会で小さなプロジェクトを行います。中には「妥協」や「諦め」を強いられる場面もあるでしょう。彼らの働きが豊かに実るよう、共に歩んでくださる神様に信頼したいと思います。
全国ディアコニアネットワーク
夏のセミナー「聖書と選挙」報告
小泉嗣(日本福音ルーテル熊本教会・玉名教会・八代教会牧師・全国ディアコニアネットワーク代表)
『選挙』をテーマにディアコニアセミナーを開催しましょう!」そう話し合われたのは昨年春にオンラインで行われたディアコニアネットワーク運営委員会の席上でした。それから開催に向けて準備を進めるも何度かの延期があり、ようやく全てが整い決定した開催日はくしくも参院選開票日翌日の7月21日でした。
「『教会で選挙を語る』と聞くと、もしかすると気になる方もおられるのではないか?」そんな危惧がなかったわけではありませんが、それ以上に日本に生きるキリスト者として、どの政党が良い悪いではなく、どのような社会を望み、つくっていくか、その責任を果たすために祈り、学び、語り合う必要性を感じての開催でした。
講師としてお話しいただいたのは、日本キリスト教団大泉教会の会員であり、教団や弁護士会、地域等でさまざまな活動をしておられる伊藤朝日太郎弁護士です。残念ながら参加を熱望した最近選挙権を得た世代の姿はありませんでしたが、それでも全国から32名の方が東京池袋教会に集まりました。
5年ぶりに行われたセミナーは永吉秀人牧師の開会礼拝からはじまりました。永吉牧師はコロサイの信徒への手紙1章24節のパウロの言葉から「ディアコニアとはしたいことではなく、すべきことをすることであり、それがキリストが負っておられる痛みを共に担うことにつながっていく」と、私たちに与えられた使命のようなものを提示してくださいました。
続く講演で伊藤弁護士は「聖書に選挙を尋ねる、というのはなかなかハードルが高いです」と前置きをしつつも、使徒言行録の使徒選出やローマ教皇の選挙など、キリスト教の「選挙」の歴史にはじまり日本の選挙の歴史までをおおまかに、そして現行の日本の選挙制度について詳細に解説をしてくださり、そこから選挙権を持つ私たちに「できること」と「なすべきこと」を丁寧にお話しくださいました。特に印象に残っているのは、「選挙」とは開票が終わるまでを言うのではなく、むしろ開票が終わった後が大切であるということでした。私たちには、自分が選んだ候補者が、また選挙で選ばれた議員が、選挙活動中に何を発言し、その言葉を選挙の後にどのようにカタチにするか、またしなかったかをしっかりと見つめ、そして本人や社会に声をあげる責任があるということを学びました。講演の後、グループに別れて「イエスさまが望む社会とは?」「生きやすさとは?」などについて交わり、分かち合いの時を持ちました。
参院選の結果をどのように受け止めるのか?それぞれ思うところはあると思いますが、選挙が終わった今から、キリスト者として、祈り、聖書に聞きつつ、なすべきことをしっかりとなしていきたいと思わされたセミナーとなりました。