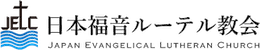温故知新『神はわがやぐら』

(詩編46・2)
10月といえば私たちルーテル教会では宗教改革の月として広く認識されていますが、ルターの宗教改革については既にたくさんの牧師たちが語ってこられましたので、私は彼が書き残した賛美歌について書きたいと思います。
ルターは言わずと知れた偉大なる説教者にして牧会者で、かつ膨大な著作を書き残しましたが、音楽家の顔も持ち合わせていました。ルターはリュートという現在のギターによく似た楽器をつま弾きながら、テノールの美声で歌ったと言い伝えられています。そうして生み出されたのが、40曲以上にのぼる賛美歌です。中でも最も有名なルターの賛美歌と言えば、教会賛美歌450番の「力なる神はわが強きやぐら」(通称「神はわがやぐら」)でしょう。宗教改革を覚える10月に入ると、この賛美歌の出番はどこの教会でも格段に多くなるのではないでしょうか?私が勤める九州学院でも、この賛美歌は10月の歌として毎年選ばれています。終始四分音符で刻まれた確固とした音型で歌われる旋律は、明朗で力強く、歌っていると元気が出てくる賛美歌だと思います。この賛美歌の旋律を使って、バッハやメンデルスゾーンが作曲した『カンタータ第80番』や『交響曲第5番』も名曲として知られています。
ところが、私たちに最もなじみのあるルターのこの賛美歌の原曲は、リズムが多少異なっているのです。2021年に出版された『教会讃美歌増補 分冊Ⅰ』をお持ちの方は、16―1番を開いてみてください。その譜面を見ると、二分音符が主体となっているものの四分音符や八分音符まで使われていて、シンコペーションが随所に登場するやや複雑なリズムで書かれています。そもそも当時の記譜法にならって拍子の記載がありません。だから、これを大人数で声を合わせて歌うのはなかなか難しいのではないかと思います。したがって、この賛美歌はもともと信仰者が一人静かに自らを省みて、神に祈りをささげる際に歌われることを想定して作られたのではないか?と言われています。実際、ルターがこの賛美歌を書いた時期は、宗教改革ののろしを上げて意気軒高としていた時ではなく、その後の改革運動がなかなかうまくいかず壁にぶち当たって気持ちがふさいでいた頃でした。そのような時に、ルターを支えたのが「神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。」という詩編46編の御言葉だったのです。ルターは生涯にわたって精神的に何度も落ち込むことがありましたが、そのたびに彼を引き起こしてくれたのは聖書の言葉と、恵みの神への揺るぎない信頼―神はいつもわたしたちの避けどころであり、また堅固な砦でもあり、必ず私たちを守り、助けてくださる―だったのではないでしょうか。賛美歌の特徴の一つは、信仰を共にする兄弟姉妹たちと共に歌うという共同性ですが、時には一人静かにじっくりと歌詞を味わい、口ずさんでみるのも有益でしょう。
なお、このルターの代表的な賛美歌「力なる神はわが強きやぐら」(四分の四拍子で書かれたもの)は、ナチス・ドイツの時代に行進曲風に編曲され、盛んに演奏されました。それで、戦後ドイツやアメリカで出版された賛美歌集では、ルターの原曲版(拍子がないもの)も一緒に掲載されるようになり、今ではそちらの方が主に歌われているようです。このたび日本のルーテル教会も、『教会讃美歌増補分冊Ⅰ』の出版によってようやくその流れに追いつくことができました。聖書翻訳にしても、あるいは賛美歌や式文の改訂にしても、罪深い人間の歩みと歴史の中で、絶えず神のみ前で頭を垂れつつ、検証され、解釈され続けていく必要があるのではないかと思います。
ルターは言いました。「恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ」と。私たちもまた神の恵みに包まれながら、説教を通して、あるいは自らも聖書を開くことによって、信仰を見つめ直す日々でありたいと思います。
『家族と音楽を奏でるルター』
Luther in the circle of his family 1875 signed b.l.


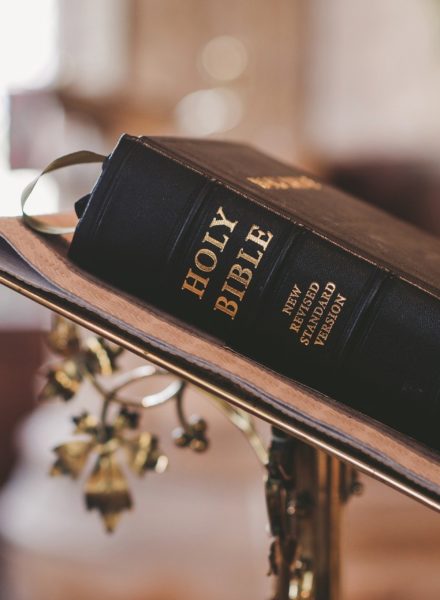






」-520x312.jpg)