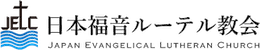これはいったいどういうことなのか
「人々は皆驚き、とまどい、『いったい、これはどういうことなのか』と互いに言った。」 (使徒言行録2章12節)
人には自分の力(理性)で知ることができるものとそうでないものとがある。
ルターが気づいたことでした。宗教改革に身を置いて聖霊だけが教えるものがあるとルターは悟ってゆきます。「私は何もしなかったのだ。みことばがこのすべてを引き起こし、成就したのである」(「四旬節第2説教」1522年3月10日※)と述べたのはそのような思いからであったのでしょう。その思いはルターその人のものでありながら、同時にいつの時代のキリスト者にも共通する体験となります。実際、それは教会のはじめからあったものでした。使徒言行録2章に記されている聖霊降臨の出来事です。そこで〈教会の誕生(聖霊降臨祭)〉から〈教会の歩み直し(宗教改革記念)〉を結び合わせる聖霊の働きに思いを向けたいと思います。
使徒言行録2章にある聖霊降臨には「一同」と呼ばれる聖霊が降ったという人々のほかに、その傍で「これはいったいどういうことなのか」と驚き戸惑う人たちがいました。この日から人々は聖霊を受け、宣教に本格的に乗り出します。主の言葉を伝え、信仰の伝播がはじまります。しかし、そこに別の人たちがいたことも使徒言行録はきちんと述べています。最初の聖霊体験にこの人たちの戸惑いと驚き、意外性とつまずきの体験が含まれていることには大切な意味があったと思います。
もし仮に聖霊降臨が「一同」と呼ばれる一部の人たちだけの話なら、当人に重要であっても、他の人々にはほとんど関わりのない話です。聖霊降臨が誰にあったかではなく、次に何が起こったのかが使徒言行録の関心事です。そうして2章から「一同」と、驚き戸惑う人たちの物語がはじまります。私たちはみな、この物語を生かされているものでもあるのです。
聖霊が注がれてこの人たちが気づいたことがありました。事の始めに、自分たちの言葉と思いと計画を超えているものがあるということをです。宣教のはじめに良い思いがあり、その終わりに良い業がある。私たちの業ではありません。旧約聖書のはじめに「光あれ」(創世記1・3)といった御業についてです。
私たちには教会の門をくぐったり、洗礼を受けたり、新しい何かをはじめるときに自分なりの動機やきっかけがあります。いろんな出会い、導き、出来事があります。いずれも大切ですが、聖霊を軸に考えるとさらに大切なことに気づきます。
そのはじめに神が事を起されていた。それを測りがたいものとしてキリスト者は受け入れます。時に口ごもりながら、時に迷いながらです。そして信じた通りに生きて歩んでいこうとします。そこに人の行き交いがあり、神の導きがあることを心の眼で互いに見ようとします。
最初の聖霊降臨祭には異なる人たちがいて、その日の出来事にはつづきがありました。同様に、信仰生活には自分を超えて、他者がいて、相手があることに気づく時があり、使命や託せられたものがあることを心で受け止める時があります。それがなかったら教会や信仰生活は、片方の翼で飛んで行こうとするようなものです。初代教会でいえば、弟子たちや周囲の人で、聖霊が降った、恵まれたといって喜び祝い、やがてその人たちがいなくなれば終わってしまう信仰です。
使徒言行録は人から霊へと視線を転じます。聖霊の行先へと自らの歩みを重ねてゆきます。2章12節のつまずきは、続く41節の教会の誕生へと跳躍します。「ペトロの言葉を受けいれた人々は洗礼を受け、その日に三千人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった」(使徒2・41〜42)。 使徒言行録は28章で終わりますが、この聖霊の働きは終わっていません。そのつづきが次の世代の人々によって担われ、さらに福音は手渡しされ、ここまできています。そのはじめに主の言葉があり、聖霊の導きがありました。宗教改革500年の時を刻むとき、「聖霊だけが教える」ものがあることを心に留めたいと思います。
日本福音ルーテル田園調布教会・日本ルーテル神学校 宮本新牧師