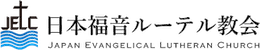るうてる2011年5月号
説教 「あの方は復活なさったのだ」
ルカによる福音書23章26節~24章11節
春先、あるご高齢の方が召天されました。葬儀の際、ご家族が介護をしていた時の様子が思い返されました。「お父さん」と声をかけ、顔をさすり、手を握る。その時と同じように、丁寧に葬りをされる様子を見た時、悲しみに秘められた「新しき命」の萌芽を見るような思いでした。十字架と復活の間に、イエスを愛していた人々は何をしていたのでしょうか。詩人ウェンデル・ベリーは、イエスの死を嘆き、葬りの準備をする「婦人たち」に復活への道筋を見ています。
“私は十字架のキリストを知っている。
肉体と時間と私たちの苦悩のすべてのために御自身を犠牲にされた
神の独り子を。
彼は死んで甦られた。
しかし彼の痛み、孤独、死に際の真昼の闇に、だれが打ち震えないでいられるだろうか。
マリアのように、彼は死んだものとあきらめて、その墓で嘆き悲しむことがないなら、復活の朝は永遠に来ない。”
十字架の出来事には、マグダラのマリヤ、ヨハナ、ヤコブの母マリアなど「婦人たち」と呼ばれている一群がいました。2000年前のキリスト証言の大事なところをこの人たちの素朴な行為が担っています。「嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れを成して、イエスに従った」(23・27)と印象深くルカは記します。イエスが息を引き取られる時、「遠くに立って、これらのことを見」(23・49)、イエスの遺体が納められる有様を「見届け」(23・55)、「家に帰って、香料と香油を準備した」(24・56)。葬りの準備をし、墓場に行き、「空の墓」体験をした人たちであり、「死んで葬られる」イエスに伴ったのはこの人たちでした。そこに最初の復活の知らせが刻まれます、「なぜ、生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ」(24・6)。イエスの十字架を嘆き悲しんだのは弟子たちも同じですが、その嘆きは同じものだったのでしょうか。自分を嘆いていたのか。イエスの死を嘆いていたのか。いずれにせよ、十字架のイエスと「婦人たち」との距離は、弟子たちのそれと比べ、とても近いものでした。
生きているイエスを熱烈に歓迎し、従うものは多くおりました。魅力あるもの、未来あるもの、何かを実現してくれる力に人は惹かれます。しかし「死んで葬られる」イエスに伴うものは多くはありませんでした。十字架は無意味で、復活の知らせが「たわ言」(24・11)のようであったのは、生きているイエスだけが大切であり、死んで葬られたイエスは、弟子たちであっても、置き去りにするしかないものだったのかもしれません。しかし十字架のイエスに伴い、看取り、葬りの備えをする人たちが求めていたのは、意味ではなく、愛です。
もし人が、日々をただ朝が来て、ただ日が沈む繰り返しではなく、復活の希望と共に朝を迎えるならば、その真昼の闇でさえも、どんなに貴いものであったかを知らされもすると詩人はうたいます。この「婦人たち」にまっさきに良き知らせが伝えられたのは偶然ではありません。復活はただ死んだものが生き返ったという時計の針の巻き戻しではなかったのです。当たり前のように、生まれて朽ちていくという染み付いた考えが、崩れ去る時でもあるのです。復活の知らせは、私たちが生まれる前も、生きて死んだその後も、永遠の命が神の許にある、という良きおとずれなのです。ルカが伝える「婦人たち」の葬りの備えは、知らず知らずに、復活の備えでもあったのです。死がすべての終わりではなく、新しい命のはじまりであると。終わりからはじまる。痛みにふるえ、孤独と闇を共にし、途方にくれることは、永遠のいのちと切り離されてはいないのです。どうして生きておられる方を死者のなかに探すのか。あの方は復活なさったのだ!
博多教会牧師 宮本 新
ルターによせて
今四旬節のさなかにあって、私達は主の受難を想う…。
荒野の茨とあざみに刻まれた主の苦しみの祈りの声が、狂熱の裁きと憤怒の大波にさらわれ、丘の上に投げられ、十字架の下に鎮まっている…。
ここに私は立つ。そうするほかはない。神よ助けたまえ。
この祈りはルターの祈りだが、今大地震と大津波を目の当たりにした者の祈りでもある。
ルターは、チェコのヤン・フスが異端と断じられ、火刑に処せされたほぼ百年後、同じ事を主張した。それを罰するため西欧最大の帝国の王がヴォルムス議会に彼を召し出し、その説を撤回しなければ、命が保証されないことが告げられた。一五二一年四月のことだ。ルターの「否」の声はたちまち彼を奈落の渦に引き込んだが、不思議にも、彼は命長らえて、やがて新しい世界を見晴るかす場所に立つ。
私達は知っている。世の人は生の中で死の力に引きずり込まれ、恐れおののくが、信ずる者は死の淵にあってなお主と共に生きることを。
「勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている」
牧師の声 私の愛唱聖句
浜松教会 花城 裕一朗
「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか。」
(マルコによる福音書15章34節)
もともと私は物理学者を目指していましたが、大学の時、親しかった友人が心の病が原因で亡くなったことをきっかけにして、「人を励ますことができるような職業に就きたい」と思うようになりました。
彼は「いい奴」だったと思います。しかし、「いい奴」が「いい目」にあうとは限りませんでした。彼は近しい人たちの言動(たとえ悪気はなかったにせよ)のために苦しんだように私には思われました。その時から、私の心の中にひとつの疑問が巣食い始めたのです。「なぜ、正しく生きようとする人間の方が苦しみを背負わされることがあるのか。これは不条理なことではないのか。」
後に神学校に入った時にも、その疑問は払拭されてはいませんでした。そして宣教研修の時には、疑問はますます大きなものとなり、徐々に神への疑念や不満に変わり、とうとう怒りとなって私の中に鬱積していきました。遂に、宣教研修中の冬のある夜に、私は我慢し切れなくなって、神に向かって心の底から叫びました。「何が恵みじゃ」「恵みなんか何もねぇじゃねぇか」「教えてくれや」と。すると神は、私に答えてくださいました。
十字架に付けられたイエス・キリストが見えて、あの言葉を言われるのを聞きました。その時私は、イエス・キリストこそが、正しく生きようとして苦しみを背負った人間の代表なのだと悟り、神が私に語られるのを感じました。「わたしの息子こそが、おまえの言っている者であることを知れ。わたしは息子を復活させた。同じように、正しく生きようとして却って苦しみを背負う者たちを、わたしが顧みないことがあろうか。彼らこそ、わたしの息子に倣う者である。彼らの人生が祝福されているということを、おまえは信じなさい。」
今は、様々な理由のために苦しみを背負って生きている人たちと向き合う時、あの日の御言葉に私はより頼みます。「十字架の後には復活がある」と堅く信じて
信徒の声 キリスト受難劇を見て
市ヶ谷教会 石原京子
昨年の七月、渡辺純幸牧師を団長とする一行に私ども夫婦も参加させていただき、フインランドのオータカリで開催されたSLEYの大会に出席した後、十年に一度、南ドイツのオーバーアマガウで開演されますキリスト受難劇を見に行きました。
受難劇の歴史は千六百年代におきた三十年戦争の時、ペストが大流行し多くの犠牲者がでたため村人が主キリストの苦難と十字架の死、復活の劇を亡くなった人のお墓の上に造った舞台で上演したそうです。それ以来この村からペストは消え、このことを感謝して、十年に一度上演することになり現代まで続けられています。
天空を仰ぐ巨大な野外劇場に、村民の二分の一にあたる二千五百人が舞台の上で、裏方として、またオーケストラの一員として参加します。
午後二時半から休憩をはさんで午後十時半まで各国から毎日五千人の観客が訪れ、出演者の熱演に圧倒されます。これはキリストの役に選ばれた人はイスラエルに数ヶ月滞在し、キリストの苦難の生涯を肌で感じ、役作りをし、他の出演者も二年間にわたり、役になりきる生活をするところからくるのだと思います。
一幕ごとの終わりには「生きた聖画」の場面があり、しばしの間、体がびくとも動かず、画の人物になりきっているのには驚かされました。
幕の役目は五十人の聖歌隊で、横に一列に並び美しい聖歌を歌います。隊員一人ひとりもこの地の住人と聞きました。ドイツ語が解らない私ですが、エルサレム入城、ベタニアでの母マリアたちとの場面、最後の晩餐、ユダの裏切りから十字架の死と復活まで、聖書に記述された出来事を、忠実に、舞台いっぱいに、こどもたち、ろば、鶏、鳩、羊、らくだなどが共に演じ、観客もイエスの時代に引き込まれていってしまう迫力には驚かされます。
この地上で起きた二千年余前の出来事を三七六年間忠実に引き継いでキリストの愛を伝えていくオーバーアマガウの村の人々に深い感銘を受けました。
長時間の劇を見終えた各国の人々の顔には喜びと感激の表情で満ち溢れていました。
二年前から予約してくださり、観劇できたことを心から感謝いたします。
十年後は、八十を過ぎた私ですが孫に手を引かれて再び観たいと願うこのごろです。
フィンランド教育事情
生きる道
3月11日の震災の悲しいニュースは世界をびっくりさせました。そして、被災しても冷静な態度でやさしく助け合う日本人の姿をテレビで見て、たくさんの外国人が驚き感動しました。
フィンランドで「被災者の行動は日本の教育に関係がありますか」という質問を何度も受けました。日本の学校の道徳教育について学んだ私は「はい、それもあると思います」と答えました。
「日本人は自分を律し、思いやりの心で相手のことを考え、命を尊重し、社会に貢献することを大切にする国民です。」
3月16日の朝日新聞に、親戚の家に避難している10歳の兄と7歳の妹の写真がありました。ランドセルを背負った二人は、学校に行く途中に線路の上に座って一休みしていました。道路が冠水していましたが、線路に沿って正しい方向に行くことができました。
人生の嵐や悲劇は、家庭・学校教育の適切さと達成度のテストだと思いました。子どもたちを堅固で安全な道に導いたか、試練にもくじけないように育てたか、それを乗り越える希望を子どもたちに備えられたか。
大事なものだけではなく、愛する人々を失った子どもたちも多くいるでしょう。深い悲しみと命の限界に向き合った人たちをどう慰められるでしょうか。イエスは教えました「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くことができない。」(ヨハネ14章6節)死にも打ち勝たれた、命であるイエスより信頼できる道はないでしょう。だから「心を騒がせるな。神を信じなさい。そして、わたしをも信じなさい。」(同1節)
ポウッカ・パイヴィ
スオミ教会
日本福音ルーテル教会の社会福祉施設の紹介 その13
社会福祉法人光の子会知的障害者通所授産施設 たにまち光舎
社会福祉法人 光の子会 理事長 たにまち光舎施設長 岩切雄太
社会福祉法人光の子会は、知的障害児通園施設「光の子学園」(るうてる2月号)、知的障害者通所授産施設「ひかり工芸舎」(るうてる3月号)、そして知的障害者通所授産施設「たにまち光舎」の経営を行っています。
その歩みは、今から45年前、知的障がいをもつ子どもたちが安心して遊べるように、門司幼稚園の園庭を開放したことから始まります。その後、知的障がいをもつ子どもたち(青年、大人)が、生涯にわたって安心できる場所を作ろうと、保護者・教会員・地域の方々が協力して法人を設立し、光の子学園、ひかり工芸舎を開設しました。
そして、1998年10月10日に、地域の在宅の知的障がい者の働く場所(安心できる場所)を作るために、「ひかり工芸舎たにまち分場(現「たにまち光舎」)」を開設し、現在に至っています。
たにまち光舎では、現在、19歳から62歳までの20名の利用者が、毎日、さまざまな仕事をしています。また、ひかり工芸舎の利用者と一緒にクラブ活動などの余暇活動を楽しんでいます。泣いたり笑ったりいろんなことがありますが、それぞれが、たにまち光舎を自分の場所として大切にしています。だから、彼、彼女たちは、たにまち光舎を訪れるお客さんを、心から歓迎します。私は、彼、彼女たちと一緒にいると、そこにほっとできる自分だけの場所を見つけることができます。
知的障がい者のコミュニティー「ラルシェ」の創始者ジャン・バニエは、次のように言っています。「誰かを愛するとは、その人のために何かを行いたいと望むことです。しかし何よりもまず、その人の素晴らしさ、そしてその人の価値を示すために、その人の前にいることです。愛するとは相手が自分の弱さに触れるのをよしとし、その人が私を愛せるよう相手に、空間を与えることです」。
是非遊びにいらしてください。ここで、あなたのためにとっておかれた大切な場所を見つけることができるだろう、と思います。
ブラジルのイースター
カルナバル
日本でもおなじみのカルナバルはローマカトリック教会の謝肉祭のことで、聖灰水曜日の直前に行われます。四旬節になるとキリストの十字架の苦しみをしのんで悔い改めの生活に入るために飲酒や肉食は控えられていたので、その直前に大騒ぎをしたというのが発端と言われています。ブラジル各地で行われますが、中でもリオデジャネイロは有名です。
四旬節・カレズマ
カルナバルが終わるころになると、街の大きな木々は紫色の花をたくさんつけます。その名も「カレズマ」といい、「四旬節」という言葉と同じ名前の木なのです。 サンパウロの東洋人街の赤い提灯風の街灯と赤い橄欖のある大阪橋という和風情緒たっぷりの橋のあたりも、紫色で染められ、「四旬節」が来たことを告げ知らせています。教会の礼拝堂の中の典礼色も四旬節で紫色に変えられます。
パスコア(イースター)
イースターは、「パスコア」と言われます。スーペルメルカド(スーパー)では通路に急ごしらえで柱と藤棚のようなものが作られます。そして、そこにたくさんのオウボ・デ・パスコア(イースター・エッグ)のチョコレートが鈴なりのように吊下げられます。色とりどりで、いろんな種類があって、おいしそうで、買い物をしながら皆見上げて、楽しそうです。いよいよ。イースターが近づいたことを知らせてくれるのです。
パスコア前にこれを買い、パスコアの日に割っていただきます。包装紙やアルミホイルから出すと、おおきな卵の形をしたチョコレート。そしてそれを割ると、さらにチョコレートがいくつも入っているという形です。
死から生命によみがえられたキリストをお祝いするパスコア。硬い石のような殻を割って、中からヒヨコが生まれてくる卵は、キリストの蘇りを象徴するものとして昔から使われてきました。ブラジルの教会でもこれを割って、食事会でみんなでいただきました。
ブラジル・日系ルーテルサンパウロ教会宣教師 徳弘浩隆
私の本棚から
戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友香、野中郁次郎 共著
『失敗の本質』1984年 ダイヤモンド社刊
昭和20年8月の敗戦から今日まで、太平洋戦争をテーマとする類書は膨大な数が発行されているが、本書(昭和59年刊、現在65刷のロングセラー)もその中の一冊である。
本書は、太平洋戦争が生起した原因は何であったのか、なぜ戦争に突入せざるを得なかったのか、といった点には言及していない。日本軍が戦った具体的な戦闘について詳細に調査し、日本軍の「戦い方」と「負け方」を分析した上で、日本軍には合理的組織にはなじまない特性があって、それが組織的な欠陥として現れた結果、太平洋戦争を失敗へ導いたと見ている。本書の副題に「日本軍の組織論的研究」とあるゆえんである。
本書は、1939年のノモンハン事件と太平洋戦争のターニングポイントとなった五つの戦い(ミッドウエー海戦、ガダルカナルの戦い、インパール作戦、レイテ沖海戦、沖縄戦)をとりあげて、いずれも戦争を経験していない六人の若い研究者が、それぞれの戦いがなぜ失敗に終わったかを分析している。
この六つの戦いは、時期も場所も、そして、その内容も異なるが、個々の戦いを分析した結果、その敗因には共通した要素があり、それが前述した日本軍の組織的な欠陥であると本書は結論付けている。
欠陥の具体的な内容については詳しく言及されているが、紙幅の関係からその項目のみを以下に列記する。あいまいな戦略目的、短期決戦の戦略志向、主観的空気の支配、人的ネットワーク偏重の組織構造、学習の軽視、プロセスや動機を重視した評価等。
では、日本軍の組織的な欠陥の根源は何であったのか、本書は、日本軍の組織は環境の変化に合わせて自らの戦略や組織を主体的に変革できなかったことだと本書は述べている。
そして、本書が指摘する重要なポイントは、日本軍の組織的特性が、その欠陥も含めて戦後の日本の組織一般に継承されているということである。
本書は、今後、日本が何らかの危機に直面した際に、組織の欠陥が再び表面化する危険があるとして、警鐘を鳴らしているのである。
むさしの教会 川上範夫
東日本大震災におけるルーテル教会の取り組み
日本福音ルーテル教会は、3月11日に発生した東日本大震災救援活動のために、東教区の要請を受け、14日に東日本大震災救援対策本部を、本教会に設置し、その活動を始めました。今回の震災はその規模、災害の大きさでも、これまでにない大震災となりました。震災直後の夜からドイツ・ブラウンシュバイク領邦教会ビショップ・ウェバー氏のメールにはじまり、次々と世界中のルーテル教会から安否を問うメールが届きました。ルーテル教会の世界ネットワーク、つながりの大きさを知らされました。
その後、救援対策本部は、緊急支援のための物資調達、募金活動を開始しました。まず、緊急支援物資の米、味噌、インスタントラーメンを購入し、23日に第1回目の輸送プロジェクトが開始されました。その後28日、4月4日と続き、全国の教会から寄せられた物資を合わせて、4トントラック8台分が支援物資として送られていきました。
今回の震災はJELCの救援活動だけでは規模が大きすぎるとの判断から、国際基準に添ったルーテル教会の災害救援援助とその実施のためにLWF(ルーテル世界連盟)から救援活動支援アドバイザーとして、マタイ氏の派遣を要請しました。そのために日本にある4ルーテル教会は緊急議長会をひらき、「ルーテル教会救援(JLER)」を設置しました。
その後、日本福音ルーテル教会東日本大震災救援対策本部から4名の牧師が先遣隊として1週間、現地に派遣されました。仙台・鶴ケ谷教会を訪問し、藤井邦昭牧師と教会員、3つの保育園に、西教区に依頼して集められた救援物資をお届けすることが出来ました。
先遣隊は仙台教会代議員の長島兄の案内で、東北学院、多賀城市、塩竃市、名取市、七ヶ浜町などの被災地を訪問、聖公会東北教区「救援対策本部」、日本基督教団支援センター「エマオ」、仙台YMCA、宮城県社協救援対策本部を訪問し、協力、協働について協議しました。4月11日からは、仙台教会に「ルーテル支援センターとなりびと」を開設し、全国からのボランティア受け入れをおこない、各被災地ボランティアセンターに派遣しています。聖公会東北教区には、鶴ケ谷教会の青年を派遣していることも大切な働きです。
これらの働きはすべて「ブログとなりびと」http://lutheran-tonaribito.blogspot.com/にアップされ、毎日600以上のアクセスをいただいています。まだはじまったばかりの救援活動ですが、皆さまのお祈りをお願いします。
新任教師挨拶
恵みの手本として
小鹿教会・清水教会 浅野直樹
みなさん、こんにちは。この4月から小鹿・清水両教会の牧師となった浅野です。復活の主は、大失敗をしたペトロの中に主に対する小さな愛を認めて『わたしの小羊を飼いなさい』と言われました。そして、私にも同じように語られたと思い、もう一度牧師として立つことを決意しました。パウロの言葉に「わたしがこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした」というのがあります。私は恵みの「手本」になれればいい。もう肩肘張らず、教会の方々にいっぱい助けられながら主に用いられていきたい、今はそう思っています。
創り主に信頼して
甲府教会・諏訪教会 市原悠史
こんにちは。この4月から甲府教会・諏訪教会で働かせていただくことになりました。まったく新しい環境の中で、まったく新しく出会う人々と歩んでいくことに、希望と共にやはり不安も抱えていました。自分はこれから、しっかりと立っていくことができるのだろうか、と。そのような思いを抱きながら迎えた朝、牧師館を出てみると、目の前に雄大な山々が朝の光に照らされて立っていました。あまりのスケールの大きさに圧倒されている時、歌いなれた讃美歌が頭の中で流れ始めました。「山辺に向かいて我目を上ぐ 助けはいずかたより来るか・・・」この山々を創られた神様が、教会の長い歴史を導いてこられた。この私も、きっと神様が助けてくださる。そう思うと、肩の力が抜けたような気がしました。召してくださった神様に堅く信頼して、働いてまいります。